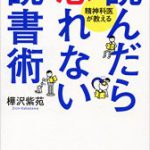こんばんは、imoです。
私の周りの子持ち友達と話してて最近よく話題に上るのが子供の「学資保険」の話。
「いつから入った方がいいんだろう?」「受取り年齢は?」「いざという時の為に免除は必須だよね」「子供の為だし親の責任だよね」「そもそもどこの学資保険が一番良いのかな」などなど
基本的に「学資保険」に入る前提の話です。
Contents
結論から言いましょう!「貯金が出来る家庭は学資保険なんて必要ありません!!」
以下で理由をご説明します。
学資保険てどんなもの?
私が彼ら子持ちに

と聞いたら

と、イマイチよく分からない返答が返ってきます。
そうです、彼らは「学資保険てどんなものか知らない、でも必要だ」と考えているのです。
でもこれは当たり前ですよね。多分私の周りだけじゃなく一般的に保険てよく分からないし、子供が生まれたら学資保険に皆入っていると聞く→じゃあ自分も入った方がいいのかな?と考えると思います
では、学資保険のことを少し説明しましょう。
学資保険には、大きく分けて2つの機能があります
- 貯蓄機能
- 保障機能
です。
そして、学資保険に入る人でメインに期待されるのは①の「貯蓄機能」になります。
要は「子供の将来の教育費の為です」
次に②の保障機能ですが、これは親が死んだ時、高度機能障害になった時にお金が払われる+払い込み免除になることが期待されます。
しかし、この保障機能部分はぶっちゃけ「学資保険」である必要はありません。この機能は生命保険でカバー出来ますし、その方がより自由度が高いのです。
そうなると、「学資保険」に求める機能は「貯蓄」に絞られます。
学資保険の貯蓄性
恐らく保険の営業やFP(ファイナンシャルプランナー)とかに相談するとこの「貯蓄機能」を強調されて勧められると思います。
そんな勧めるほどに有利なのか?
では、この「学資保険の貯蓄性」も大きく2つの機能があるのでご紹介しましょう。
- 強制性
- 利回り
1の「強制性」とはその名の通り一度保険契約をすると保険料という名目で毎月強制的にお金を貯蓄しなきゃいけなくなるということです。
貯金が出来ないご家庭に「強制的に積み立て貯金が出来るようになるので確実にお金が貯められます!」と宣伝されていますよね
実際、これは機能というほど大げさなものでもないんですよ。わざわざ保険に入らなくても習慣化してしまえば確実な積み立て貯金は普通に出来ます。
2の「利回り」ですが、「学資保険」の利回りはどれくらい有利なのでしょう?
預金と比較してみます。
2016年現在の定期預金の全国平均は年率0.025%です。
地方銀行にはもっと有利なものもあって大体年率0.2%くらいの定期預金もありました。
次に元本保証の投資商品で代表的な「国債」ですが変動10年で年率0.05%くらいになります。
定期預金よりはマシなのが国債ですね。しかし、地方銀行の利回りはそれより全然いいです。
では、「学資保険」の利回りを見てみましょう。
学資保険は返戻率という表現をします。分かりやすくいうと返ってくるお金ですね。
現在、最も有利な学資保険返戻率誇る
明治安田生命保険『明治安田生命つみたて学資 Ⅰ型』 返戻率112.6%です。
これは年率換算すると0.98%になります!
学資保険の所得控除
学資保険は、カテゴリー的には生命保険なので年末調整で生命保険の所得控除があります。
年収や他に入っている生命保険によって変わってくるのですが、
こちらの記事をまず参照下さい
学資保険は所得控除が適用され税金が安くなる
所得控除
こちらでは18年間で9万円の税金が返ってくる条件で計算しています。
また、税金は年収が上がれば上がるほど税率が上がりますので、控除においては税率が上がるほど戻ってくる税金が増えていきます。
これを利回りと考えて学資保険の利回りに差し戻すと年収300万~400万の場合大体満期利回りで5%ほどの改善になりそうです。
こちらで改めて学資保険の所得控除を含んだ年間利回りを出したとしたら年率1%ちょっとです。
凄い!一番利回りがいいじゃないか!!やっぱり学資保険は有利なんだな!
と、考えるかもしれませんね。
ちょっと待ってくださいコトはそう単純じゃないんですよ。
以下で、「学資保険」ひいては「保険商品」の貯蓄機能についての問題点をご説明します。
保険の貯蓄機能の落とし穴
- 「流動性」
- 「不確実性」
- 「割引現在価値」
- 「販売手数料」
保険商品の貯蓄機能にはこれだけのデメリットがあります。
それぞれ説明しますね
1「流動性」
保険は契約期間中自由にお金を引き出すことが出来ません。更に、保険期間の前半からほとんどの期間解約した場合元本割れを起こします。
このように保険には急にお金が必要になった時に簡単に使えないという利便性、流動性に大きな問題があります。
2「不確実性」
保険の長期に渡り契約が継続するという前提は確実なものではありませんし、仮に満期まで契約が継続するとしても、その間に金利が上昇したりすると低金利下で結んだ契約の価値は下がります。
つまり、長期契約において約束されている商品の価値は環境の変化に対応出来ないというリスクも考慮し大きく割り引いて評価しないといけないのです。
3「割引現在価値」
これは、単純に現在の100万円と20年後の100万円は同じ価値なのか?ということです。
「今80万円を貰えるのと20年後100万円貰えるのではどちらがよいですか?」との質問されたとします。恐らく大半の人はそんな「未来の100万円」より「今の80万円」を選ぶと思います。
このように現在のお金と未来のお金では、現在のお金の方が価値が高いのです。これが現在価値です。
ですので、仮に20年後の返戻率が120%だとしてもインフレ率を考えると現在価値でそんなに増えていないということになるんです。
ちなみにインフレ率は、日本は2000年代に入ってから10年ほどは実質マイナスになっていました。いわゆるデフレですね。
しかし、これはかなり特殊な状況だと考えて下さい。資本主義の前提はインフレですし日本においても2000年代のデフレ期間を含めてもより長期間で見ればインフレなのです。
現在政府は目標をインフレ率2%に置いてますが、まーこれが達成されなかったとしても歴史を見れば1%ほどのインフレにはなる可能性は高いです。
1%インフレを仮に条件として考えると20年後の120万の現在価値は約98万円になります。実質、購買力の維持でしかありません。
4「販売手数料」
保険には販売手数料というものが掛かります。
これは保険料に含まれており、解約返戻金がマイナスからスタートすることで分かるでしょう。元本割れ分は保険会社の経費なのです。
ここに、もし保障機能も乗っかると保険料が上がり解約返戻金の当初元本割れ比率は更に大きくマイナスになります。
以上保険による貯蓄機能のデメリットでした。
どうでしょう?
「流動性の面で融通が利かず予想外にお金が必要になった場合は元本割れ、更にちゃんと満期まで契約を続けたとしても実質、せいぜい現在の購買力の維持でしかないのです。」
こうなると、「学資保険」のはっきりしたメリットって貯金できないご家庭への強制性にしか無いことになります。
単なる「無理矢理にでも貯金が出来る」というメリットの為に、上記の元本割れリスク、流動性リスクなど大きなデメリットを受け入れられるのでしょうか?
私としては子供の教育資金を貯める。もっと言えば運用により少しでも殖やす方法は他にもあるので、「学資保険」に入るメリットは薄いと思います。
まず、貯金が出来ない人は以下の記事のような方法でしっかり習慣化すればそんなに難しくなく貯金が出来ます。
実は、運用率を上げるよりも節約の方が効果が高いという事実もあります。
例えば、月々2万ずつ30年間3%で運用したとして約1600万になります。一方月々5万ずつタンス預金した場合は1800円となり結果は節約し月々の積み立て金を上げた場合の方が上になります。
最強は、節約し更に資産運用でより良い利回りを生むことです
ただでさえ教育資金のような10年以上に渡る長期運用はじっくり取り組めるので良い結果が出やすいので、少し運用の勉強をして取り組んでみることをおススメします。
このブログでは、「自前の投資力」を付けて長期的にお金の心配を軽減する方法を書いていますので、是非、他の記事も目を通してみて下さい。
以上、参考になれば幸いです。