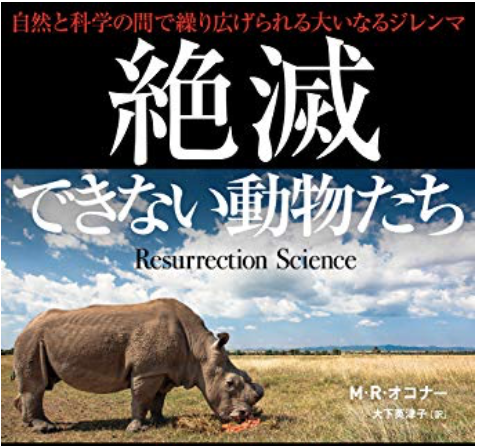
こんにちは、imoです。
今回は、読書感想文。
ここ最近は投資成績報告だけのうんこブログになっていましたが、一部の人達からまた以前のように色々な濃い話を書いて欲しいとの声がありちょこちょこ復活していこうと思っています(メルマガも終了したし)
ということで、タイトル通り「絶滅出来ない動物たち」という本を読んだ感想をば書いていこうと思います。
Contents
「種」とは何か?「自然」とは何か?「絶滅」とは何か?
まず、非常に面白かった!
一般的にも、私自身にも普段馴染みのない分野である、「自然保護」「生物保護」について色々な視点から語られています。
そして、何気なく我々が使っている「種」とか「絶滅」とか「自然」という言葉の意味や定義を深く考えさせてくれる本です。
例えば、アフリカのある滝の下にだけ生息する小さなカエル話では
人間の世界の貧困問題、パワーバランス、エゴが衝突しその生存が脅かされるのですが、ここで「そもそも絶滅とはなんなのか?」「絶命の何が悪いのか?」「カエルを救う意味は?」という沢山の問いが投げかけられます。
この小さなカエルはある滝の下にだけ生息していました。
そこで、人間様はそこにダムを建設し水力発電所を作ろうと考えます。
アフリカの貧困問題は電力不足の影響も大きく、一年を通して水量が安定しているカエルの滝が目をつけられたのです。
ご想像の通り、発電所を建設すればカエル達の生息環境は変化し繊細なカエルは絶滅してしまいます。
人間様の選択肢としては事実上、
- カエルを別の環境で保護し生かせないか?
- 発電所建設後も、同じ場所で人工的に生かせられないか?
の二択。
パフォーマンスとして環境アセスメントみたいなことは実施されますが、恐らく「小さなカエルのために水力発電所を建設しない」という選択肢は初めからなかったことでしょう。ここは経済問題が優先。
その後、カエルは保護のためアメリカの研究所へ移送されようとしますが、始めタンザニア政府は希少種のカエルから医療に使える成分とかが取られかねないと懸念し、国から出そうとしません。(人間のエゴ)
そして、発電所建設後に人工的に作ったカエルの生息環境にも年間で莫大なコストがかかります。
「貧困で困っているから発電所を作ったのに、そこに生息する小さなカエルを生かすために莫大なお金をかけていることはどうなのか?」
という当然の批判も現地の人からは出てくる。
人間の行動や都合で環境を変えそこに生息する生物を人工的に保護する。
この流れは本書を通して繰り返されるパターンです。
「絶滅」とは何を指すのか?
「絶滅」の定義は、簡単なようで非常に複雑で定義が難しいことをこの本を読んで思い知らされました。
説明したカエルの例では、既に彼らの生息環境はこの世界から消滅しています。
そして、彼らはその生息環境でしか生きることは出来ないのです。
そんなカエル達を研究所の人工的環境で保護し続けることになんの意味があるのでしょう?(しかも莫大なコストをかけて)
この小さなカエル以外にも、もはや生きていくための環境が消滅してしまって絶滅に追い込まれている生物達は沢山います。
先日もホッキョクグマのニュースもありました。
このような生息環境が無くなってしまった「種」を無理矢理人工的に生かす意味はあるのでしょうか?彼らは、ほとんどの場合「自然」には帰れません。
残すべきはDNAか文化か?
他にも、残すべきものは何なのか?という問題があります。
仮に、遺伝子技術が更に発達しDNAからあらゆる生物が蘇らせるようになり、今生きている個体が消滅してもいつでもDNAから復活させるジュラシックパークな世界が実現出来たとしたら、それは「絶滅」とは言わないのでしょうか?
生物は、当たり前ですが自分の設計図であるDNAと生息環境によって成り立っています。
例えば、ゴミを漁る都会のカラスは環境に適応した結果の「文化」を持っています、一方でDNAから蘇らせたカラスはもしかしたらゴミを漁ることはないかもしれない。(文化が失われる可能性についても本書で書かれています)
以前のカラスとは見た目は同じでも似て非なるものとなります。
そもそも復活させても過去に生きていた環境が無くなっているので生きていけないというパターンも沢山あるでしょう。
また、DNAからいつでも復活させることが出来るなら今生きている個体を保護する必要性もないよね?という考え方をする人も出てくる。(脱絶滅)
つまり、DNAだけ残すことで生物保護は達成されるのか?という問いです。
「種」とは?
そもそも「種」って何?ということもこの本を読んでいると疑問になってきます。
実際の生物世界では、純粋な「種」なんてほとんどいません。
必ず交雑している。
しかし、保護すべきは純粋な「種」という考えが生物保護世界にはあるようです。
仮に交雑してしまうと、もうその生物は保護対象ではなくなるとか。
更に更に、人為的に環境を変えた「種」の例で、数十年の間にDNAレベルで変化(進化)してしまう事例もあったとのことで、時間という概念を持ち込むと「絶滅から守るべき純粋な種」などいないと言える感じ。
生物は、常に変化、淘汰にさらされていて決して安定している存在ではないんですね。
常に環境適応しようとしていますし、突然変異も起こっている。
そこに、それぞれの生物固有の「文化」なるものも絡んで保護すべき「種」とは何なのか?がもうよく分からない・・・笑
ハイパーオブジェクト
ハイパーオブジェクトという言葉があります。
ここまで書いてきたように、生物世界は一定ではないですし、種の絶滅も一様には語れない。
生物は、DNAと環境のセットで更に多くの相互関係によって存在しています。
そして、人間はもはやあらゆる場所に存在し、テクノロジーの進展によって自然環境にも大きな影響を与えており、その環境変化によって絶滅に追いやられている生物が多いのも事実。
そんな時代を人新世というようですが、人間が関わることによって地球上の自然は変化し、そもそも「ありのままの自然」という概念もあやふや。
一方で、本書に登場するクジラのように、人間の力が及ばないレベルの地球環境によって生き延びている生物もいます。
このクジラは保護しようにも人間様には不可能。
直近、大きく数を減らしたのは人間の影響のようですが、このクジラ達を増やしたり保護したりということをするには、まだまだ分かっていないことが多く、想定される保護活動も物理的に不可能という巨大な存在です。
そんな諸々の事象が複雑に絡み合って今の大きな絶滅の流れを作っている・・・というのがハイパーオブジェクトという概念。
単純に生物保護も絶滅も語れないけど、多くの生物が絶滅の危機に瀕していることは事実であって、人間はそのな大きな流れの中でどう振る舞えばよいのだろう?という大きな問いを投げかけてこの本は終わります。
DNAを保存するだけでは多分ダメ。
でも、人間の活動による環境への影響は中々減らせない。
かといって、このまま絶滅していくのを指をくわえて見ているのは、人間にとってもリスク。
とにかく、色々考えさせられますし、知らなかったことを知れる知的好奇心も刺激されます。
人間は非力なようで巨大な力を持っていて、何か希望する特定のことにおいてはまた非力という複雑な存在だなぁと、人間という「種」についても改めて考えてみたくなる本です。
以上、興味がわけば是非読んでみて下さい。
それでは、また

















