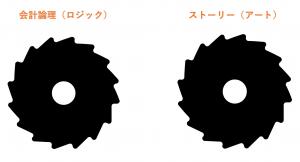こんにちは、imoです。
さてさて、今回は昨今流行りのいわゆる「サブスクビジネス」を呼び水に「そもそもビジネスとは?」ということについて私が考えていることを特に需要があるかどうか知りませんがちょっと書いていきます。(多分ない)
Contents
資本主義の世界ってなんだ?
まず、資本主義のこの世界について整理します。
別に資本主義の厳密でアカデミックな議論をしたいとか、株式投資の正解やビジネスの正解を語りたいとかではないので、ゆるっと読んでもらえれば幸い。
個人的に、この資本主義世界は以下の両輪で動いていると考えています。
- 会計論理(ロジック)
- ストーリー(アート)
メルマガを読んでくれていた人達には耳タコですがこの「ロジックとアートのバランス」は人間世界を理解する上で非常に大事な視点です。
どんな場面でもこの二軸で考えないと理解が浅くなる。
そして、世の中の頭良い人、高学歴者はロジックによりがちなのは指摘しておきたいと思います。
「論理的にこうでこうだからこうなるはずだ!」
これまたメルマガでは口酸っぱく言っていましたが、ロジックの限界は案外低いところにあるので、ロジックロジック(コスパとかファクトとかよく言ってる人はこの傾向強し)している人は例外なくその内大きな落とし穴にはまるでしょう。
・・・ちょっと脱線。戻します。
会計論理(ロジック)
会計論理というのは、いわゆるB/S,P/L,CFなどの数字の把握や分析、全体としてのお金の流れのお話ですね。
これが、資本主義の根底に流れる論理です。
この論理によれば、「自己資本に対するキャッシュの創出をいかに効率よく行うか?」が焦点となります。
いわゆるEPS(一株利益)をいかに出すか(大きくしていくか)?
そして、EPSを生み出す=BPS(一株純資産)増加を継続的に達成できるか?
これが達成されるから株式投資はプラスサムとなりえます。
ゴリゴリのバリュー派の人の中には保有資産評価と株価の乖離があればEPSもBPSの増加もいらん!という人がたまにいますが、EPSがマイナスでBPSもゴリゴリ毎年下げていくような企業にバリューなんてないと個人的には思います。株価は上がることなく、いずれ保有資産評価と株価はバランスするでしょう。
この意味で、個人的にはバリュー派といっても最低限EPSプラスのBPS増加自体は期待していると思いますし、グロース(ここでの定義はEPSのダイナミックな成長期待派くらいな感じ。うーん、ぼんやりしてますねぇ)も見ているところは同じかなと。
要は、EPSが出るの?ってお話。
また脱線。
あまりここもバリューやグロースの定義が曖昧なまま深入りはしたくないので話を戻します。
ということで、多くの”ちゃんとした”株式投資家さんは、これ(会計論理)をよーく研究勉強しています。
余談ですが、会計士や税理士さんは別に上記を追求している気はしないですね。株式投資家の方がこの視点では強いと思います。
全てを数字から読み解き、仮説を立てて、その企業のビジネスの強みを探る。
とても正しいアプローチに聞こえますね。
そして、実際半分以上は正しいアプローチだと思います。
ストーリー(アート)
次、両輪のもう一方ストーリー(アート)のお話。
こちらは、具体的にはそのビジネスが思い描く実現したいビジョンとそこへ向かうストーリーのことです。
そもそも、起業家がビジネスを行う以上実現したいビジョンがなければいけない。
ビジョンのない起業家はそもそも起業なんてする必要はありませんし、ただロジック的に儲けられそうだという理由でビジネスを始めた場合もそのビジネスはほぼ100%失敗に終わります。
私の経験から見える傾向として、ロジックばかりの儲けの構造に注目してビジネスを始める人は、よくブルーオーシャンの話をします。
このブルーオーシャンの話も聞き齧っただけで「誰も敵がいない美味しい海」という雑な理解で、自分のやるビジネスはこの海で行うのだ!と豪語しますが、彼らに本当のブルーオーシャン戦略とは、自らが切り開く新たな海のことであって、既に存在する美味しい海なんかではないということを話すと意気消沈してしまい起業へのモチベーションはだだ下がり。
ブルーオーシャン・・・ビジネス上の堀とも言い換えてもいいでしょうか。勿論、ビジネスを行う上でこの「堀」について語ることは重要なのですが、総じて理解が浅いと個人的には思っています。
根本的に「ビジネス上の堀」は、”既に存在しているもの”でもありませんし、”真似するだけで簡単に手に入れられるもの”でもないのです。
私が知る限り、「ビジネス上の堀」を築くにはビジョンとストーリーが必須であり、その堀が一度築かれても常にメンテナンス(ストーリーの動きがある)をしないとすぐに埋まると考えています。
ブルーオーシャンの話と同じ。
常に動いていて自らの力で切り開く新たな海を生み出し続けることが「ビジネス上の堀」を維持することになります。
ビジョンやストーリーが必要ない領域は、恐らく「規制業界」「不動産絡み」の二つの領域に限られるでしょう。
この2領域は、正直特殊な海だと感じます。一度参入し堀を築いてしまえば、比較的メンテナンスしなくても楽にキャッシュが生まれる領域です。(都心一等地の大家になりたい人生でした)
人間だもの
それでは、なぜこのストーリー(アート)が大事なのか?
その理由は、私たちの生きる世界は”人間世界”だからです。
私たち人間の脳は基本的にストーリーにしか反応できないとも言われています。
人間は、記憶するにも単体で意味のないものは理解出来ないし覚えられない。
文脈があり、その意味を理解し、そして感情が動く。意味も文脈によって変化することが多々あります。
そして、私たちは、感情の重み付けによって何かしらの具体的な判断に行き着きます。
マーケティングの世界でも、「消費者は感情で購買を決断し、後から論理で自分を説得する」と言われていますしね。
例外なく私たちの認知はこの流れでしか世界を理解できません。
だから、ロジックは最低限必要だけど感情を動かすアート部分も必須なのです。
こちらは投資家においては多くの場合軽視されている印象。書いていてなんですが、多分のこの記事の話も投資家はあまり興味を持たない気がします。
「で?それが投資で儲ける為にどう関係あるの?ビジョンやストーリーなんて知らねえよ」みたいな
(この記事の視点はどちらかというと起業家の視点です。投資に応用するか?はその人次第でよろしく。)
雑な理解の人はストーリー(アート)部分を単なるブランドビジネス、信者、ファンビジネスとしか理解していません。
全然違います。
購買の意味づけとして常に人はストーリーを必要としていますし、そのビジネスをスケールさせる(ビジネス上の堀に繋がる)にも多くの人にストーリーの共有が出来なければいけない。
そして、「ビジネスモデル」というものは、ストーリー(アート)を会計論理(ロジック)で上手く表現する、最適化する際に構築するものです。
言ってみれば、ビジネスモデルはアートとロジックの仲立ちをするものみたいな位置付け。
なので、根本的にビジョンやストーリーのない起業家がビジネスモデルばかり追求し、成功しているビジネスモデルをパクっても意味はありません。それっぽいだけで終わる。
ということで、前置きが長くなりましたが以下サブスクについて(笑)
サブスクありきじゃない
サブスクリプション、つまり月額課金のような継続的に支払いが発生するシステムですが、最近どこもかしこもサブスク、サブスク言ってますね。
しかしながら、そもそも月額課金なんて昔からある話です。
その視点からだと家賃とかなんてサブスクの走りなんじゃないですかね?
あと、バブル期とかに流行った月賦。
高額な商品を分割買いする制度ですが、これも見方としてはサブスクです。
今でもクレカで分割支払いは割と普通じゃないでしょうか?
サブスクなんて別に新しいシステムでも何でもない。
じゃあ、何で昨今みんな「サブスク」「サブスク」言ってるのか?
その理由は、大きく二つかなと個人的には考えています。
- シェア的な価値観(部分利用的価値観)
- ネット経由でソフトウェアがリアルタイムでアップデート可能になった(変化の早さ)
の二つです。
1は、そのまんま必要な部分を必要な分だけ小分けで・・・みたいな感じ。
サブスクは前述の通り、見た目は単なる分割払い的です。
昔の月賦とかと違うのは、支払い限度が決まっていないこと。
一回で辞めてもいいし、ずっと継続しても良い。ただし、継続するほど総支払額は買い切りよりも高くなる。 (機能がアップデートされるけど)
2は、単純に環境要因です。
代表的なのはAdobe。
サブスクに移行する前は、基本的に1年半程度の間隔で新製品を出して、それを買い切り販売するビジネスモデルでした。
ちょっと前のIT業界は、いわゆるムーアの法則(一年半〜2年で半導体性能が倍になる)が支配しており、ソフトウェアのアップデートもこのタームで行われていたことが一定期間での買い切り販売の大きな理由の一つでした。
しかし、昨今開発スピードのアップとネット回線の高速化、クラウド技術により、リアルタイムでの一斉アップデートが可能になり、一定期間での買い切り販売ではあまりにスピード感がないということで、サブスク化したというのがざっくりとしたAdobeのサブスク化の裏側です。(ムーアの法則は逆に限界が囁かれています)
つまり、何度もアップデートを重ねて完成度を上げたり、新機能を追加するソフトウェア業界とサブスクは相性が良い。(MicrosoftがAdobeを踏襲するのも当然。元々延々とアップデート商法でしたし)
経営や開発することを考えてもサブスクは収益が平準化し安定した開発が可能になります。
はい、まとめましょう。
昨今のサブスク化のブーム?の大きな要因は、⑴部分利用の価値観、⑵アプリなどのソフトの頻繁なアップデート対応、によります。
それ以上でもそれ以下でもない。
部分使用していて価値を感じなくなれば簡単に切られますし、アップデートが遅い(変化が遅い)と切られます。
サブスクのシステム自体は、全然安定したビジネスでも何でもありません。
そして、サブスク自体にビジネス上の優位性なんてありません。
この点、会計論理からみればサブスクは安定収入になりますし、開発計画も立てやすい、収入もブレのある新規販売ではなくストック的である、しかもそのストックは毎年積み上がっている!サブスクモデルの成功だ!・・みたいな観点から語られるだけです。
継続課金されることの難しさ
しかしですね、ビジネスとして長期でお金を支払い続けてもらうってめっちゃハードル高いんですよ!
消費者側は、毎月支払い通知が来て「ああ、またお金が減った」と思うわけです。
月額数百円でも毎月通知が来るたびに消費者の意識に上ることは、出来れば忘れてくれた方が良いサービス提供側としては不利な要件です。
「続ける意味ないな」と思えばワンクリックで解約の憂き目にあいます。(解約手続きを面倒臭くしている姑息な業者も多いですね)
さて、では長期で継続課金させる為に必要なモノとは何でしょうか?
それは、表面的には「払っている対価以上の満足」を常に感じられるか?です。
で、これを感じさせるには端的に言って、そのサービスや商品が提示するイメージや理想に向かって歩くストーリーを感じさせるか?によります。
言い換えると、「あなたが望む世界を叶えるであろう期待と永遠の未完成感」がないと長期で継続してお金を支払おうなんて人は思いません。
そして、顧客自身がそこへ向かって歩んでいる(変化、成長している)実感が伴うとより強い。
これらを感じないと、初めは興味を持って課金しても途中ですぐ飽きられて別のサービスや商品へスイッチされます。
ビジネス上の堀ってやつ
投資家は「ビジネス上の堀」という言葉が大好きですが、その堀の結果だけ見ていることも多い気がします。
よく言われるのは、コスト優位、技術的優位、スケールメリット、ネットワーク効果等々
しかし、それらの堀は万能ではないし永遠も約束しません。
つまり、長期継続課金も約束しない。
その堀に安住し、胡座をかき、崩壊していったビジネスは沢山あります。
崩壊した企業達は、ビジネス上の堀があることに安住し、その堀がどうやって掘られたのか?に意識がいかなくなった結果、崩壊していったのです。
ビジョンに向かってストーリーが動いていることが重要
スケールメリットやコスト優位、ネットワーク効果も初めからあるものではありません。
商品やサービスがスケールした結果、得られる堀です。
そもそもスケールする際に必要なものは何か?という話。
そして、スケールした後もその堀を維持する為に何が必要か?という話。
企業は常に変化しなければいけないとよく言われます。
動いていなければいけない。
強固な堀が築かれた後も、変化していかなければいけない。
その変化は、それぞれの企業が提示するビジョンへ顧客を伴って向かうストーリーに沿っていることが必要で、そこに顧客は継続的にお金を払う。
これが、サブスクの要点ですし、ひいてはビジネスの要点です。
ストーリーが止まるとミクシィのように圧倒的な地位からでも容易に滑り落ちます
まとめ
ビジネスの理解は、会計論理だけでは足りませんしビジョンだけでも足りません。
両方が必要です。
そして、二つを繋ぐ表現手段としてビジネスモデルが登場する。
ビジネスの大目標はビジョンの実現であり、それは会計論理と結びついて長期のEPS増加を伴いBPSも増加することに繋がります。
ビジネスとしては、崇高なビジョンを掲げても利益が出なければ継続性に疑問符が付きますし、会計論理的にお金が回っていてもビジョンがなければ長期で顧客を惹きつけれられず、ブルーオーシャン(ビジネス上の堀)も切り開けない。
(この点、収益を上げないでビジョンの実現のみを追求するモデルも近い内出てくる気がしている。お金の価値はどんどん下がっています。資本主義とは別の論理ですね。共感とか協働とかそんな感じ)
両方が上手く回ることが大事。
繰り返しになりますが、長期のEPSを得る、つまり顧客から長く愛され利用されることこそを目標にすべきでビジネスモデルとしてサブスクにすることには何の意味もありません。
そして、会計論理だけの視点から、ROEガーとか利益率がーとか語っていても弱いと思いますし、長期的なEPSを考える際にも片手落ちになると思います。
以下、余談
株式投資においてもロジックとアートのバランスは重要と考えています。
短期トレードはテクニカル分析しかり市場参加者の心理(アート)要素が強いですし、長期投資は企業分析(ロジック)が強い。
恐らく、最も安定的、効率的に稼ぐという意味ではロジックの分析が出来る上に市場参加者の心理も考慮出来る人でしょう。
どっちかだけでもナンセンス。
株式投資の場合は、それぞれが考えている投資期間、価値観(儲け至上主義者、会社を応援みたいな応援者など)、上記のアートやロジックが絡み合い複雑怪奇なので通常他人との合意は得られないでしょう。
投資法などの議論は宗教戦争に近い。自分の信じる神を崇めるだけで他の神は悪魔だ!というだけ。THE 不毛
どの投資スタイルを取るかは、個人個人の適性と好みの問題です。
投資をしたいなら、まず自分を知ることが大事だと個人的には思いますけどね
以上
それでは、また