
「信用収縮」という言葉を聞いたことはありますか?
金融工学が発達した現代ではまさに”主役”とも言える役割を演じていますが「ギリシャ危機」、「リーマンショック」などの例を挙げるまでもなくこれは諸刃の剣でもあります。
本日はその基本を確認しておきたいと思います。金融リテラシーの初歩ですね。
Contents
銀行はなぜ潰せないのか?
よく金融危機の時に小さな企業は救わないのに、大手銀行に関しては国が救済することに非難が集まります。
これは銀行の振る舞いを見ていれば同意できる非難です。(本当、痛い目に合えばいいのに・・・と個人的には思いますよ)
しかし、国としては「銀行」を簡単には潰せない理由があります。そして、それは一般国民の為でもあるんです・・・
では、まずは「銀行」の役割を簡単におさらいしましょう。
銀行の役割
ここでは大雑把に確認します。
銀行は何をしているのか?
よく「金融機関は何も付加価値を生み出していない」と非難されます。
確かに、メーカーであれば原料から付加価値のある製品を作ります。これは一番分かり易いですね。
この付加価値がいわゆるGDPに直結します。
では、「銀行」は何をしているのか?
銀行の役割は、一言で言うと「経済の潤滑油」です。
一般市民や各企業などから貯金(預け入れ)と言う形で資金を調達し、その資金を企業に貸し出します。
このように資金の出し手と借り手の仲介をするのが「銀行」の役割です。そして、銀行はその仲介に伴う金利差を利益としています。
この一連の流れで「銀行」はGDPに寄与するような付加価値を生んでいませんね?(余談ですが、どこに「銀行」の付加価値はあるのか?というとGDP目線で言うと「高い人件費」です。国内の人件費が増加することはGDPに寄与します。)
銀行は確かに付加価値をそのビジネスでは生みません。しかし、経済社会になくてはならない存在なのです。
資金の循環が滞ると経済は停滞します。なにか付加価値を「銀行」自体が生むわけではありませんが、経済全体に貢献することによって経済の規模拡大やスピードに貢献します。
これが、「銀行の役割=経済の潤滑油」という意味です。
信用創造と信用収縮
上記の「経済の潤滑油」という機能を膨らませたのが、「信用創造」という機能です。
これは銀行特有の機能で、非常に複雑絡まって実態以上の経済規模に見せかけます。
簡単に図で説明しましょう
これは、まず最初にM社がA銀行に100万円預け入れます。
当然、A銀行には100万円の定期預金残高が出来ます。そこからA銀行は懇意のN社に「借りてくださいよー」と90万円融資します。
N社は、懇意のA銀行が低金利で貸してくれると言うし、いざという時の為にキャッシュを厚くしておこうと考え借り入れました。しかし、すぐに使う資金ではなかったので、今度はB銀行にそのまま90万円預け入れます。
B銀行にN社の定期預金残高90万円ができ、同じように懇意のO社に80万円融資します。
O社は設備投資の為に借り入れましたが市況の変化で今すぐの設備投資は控えようと経営判断。そして、一時的にC銀行に預けておこうと考えました。
C銀行にはO社の定期預金残高80万が出来・・・・・みたいに複数の企業、銀行が絡んで始めの100万円の預け入れがどんどん膨らんでいきます。
このように、現物の資金は始めの100万円だけですが、どんどん”信用創造”が行われいつの間にか、複数の金融機関に数倍の残高が計上されるのです。
上の図でA銀行はP社のことなんて知りません。しかし、P社が倒産しC銀行が回収不能になった場合めぐりめぐってA銀行も危機に陥ります。
この信用創造の逆回転現象が”信用収縮”と言います。
現実にはこんな単純ではなく複雑に絡み合った構図になっており、何処が倒れれば何処に影響するか?が正確に把握できません。そうなると皆疑心暗鬼になり必要以上のダメージにも繋がりかねないのです。
「キプロス危機」
当時、キプロスは、GDP(国内総生産)がユーロ圏全体の0.2%の小国であったものの、同国の銀行資産はGDPの約8倍、預金残高は約4倍に達しており、金融機関があまりに巨大になりすぎていました。その要因として、かつて観光以外に主要産業がなかった同国が、高金利と低税率を武器とした金融立国(オフショア金融センター)を目指したことがあり、それがうまく成功し、ロシアなど海外から「タックスヘイブン(租税回避地)」として多くの資金が集まりました。
一方で、歴史的にキプロスは、住民の大半がギリシャ系(公用語もギリシャ語)で、ギリシャとの結びつきが強い中、ギリシャ危機により、同国も必然的に危機に陥ることになりました。実際、2012年6月にEUに支援を要請したものの、しばらく棚ざらし状態が続き、2013年3月に資金ショートが迫って救済を求めた際には、EUとIMFが100億ユーロの資金を貸す代わりに、キプロスの預金者にも58億ユーロを負担させるという「厳しい策(異例の預金者負担)」を求めたことで、一時大混乱に陥りました。
出典 http://www.ifinance.ne.jp/glossary/world/wor030.html
小国キプロスがユーロ全体を揺るがす問題なったのも「信用収縮」が原因です。
人や文化のように動きが鈍いものと比べて特に金融は移動力がハンパではないのでグローバルな影響は当たり前。もはや経済問題は1つの国の国内問題で済まないことなのです。
やはり「銀行」は簡単に潰せない
信用収縮の怖さはなんとなく分かったと思います。
一企業を潰すのとはわけが違うのです。「銀行」を潰すということは連鎖的に複数の企業、金融機関が潰れる可能性を孕みます。
そして、始めの「銀行」の役割で言及したように銀行は経済の潤滑油であり、その資金の出し手は「我々一般国民」でもあるのです。
「銀行」を潰すということは、我々一般国民の資産にも大きな影響を与えます。
取り付け騒ぎなんて起きたら社会的大混乱に陥るでしょう、その上企業の倒産です。そうなると国民生活に大ダメージになる・・・
国はそれだけは避けなければいけません。だから銀行は潰せないのです。
「銀行」の罪
ここ最近の銀行は、本来の「経済の潤滑油」の役割を果たしているのでしょうか?
利益に占める「手数料収入」が大き過ぎないでしょうか?
個人投資家で言い換えると純粋な投資行動による資産運用ではなく、ノウハウ販売のような物の小売業で利益を上げているようなものです。
そして、分不相応の給与を得ていないでしょうか?
どうせ潰せないという高をくくり、やりたい放題している経営陣は本当に報いを受けるべきだと思いますね。
その意味でリーマンブラザーズの件はサプライズでした。
あの件から金融機関は何か学べたのでしょうかね?同じことを起こさないよう歴史に学び、本来の「銀行」の役割をもう一度思い出して欲しいものです
以上、信用創造、信用収縮についてでした。多分これからも「なんとか危機」は起こります。資本主義の暴走した姿がこれなんである意味不可避かと
今後あなたが経済ニュースを見る時により中身が分かるようになると記事を書いた意味があるってもんです。それでは、また
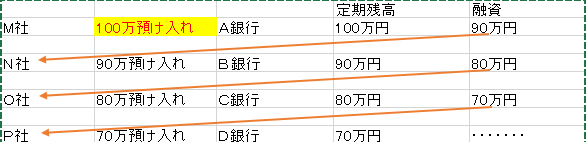






![人と違うモノが見たかったら「視点」を増やすと良い[読書感想、異端の数0]](http://assetsjin.com/wp-content/uploads/2016/12/0d448f9f-150x150.jpg)










