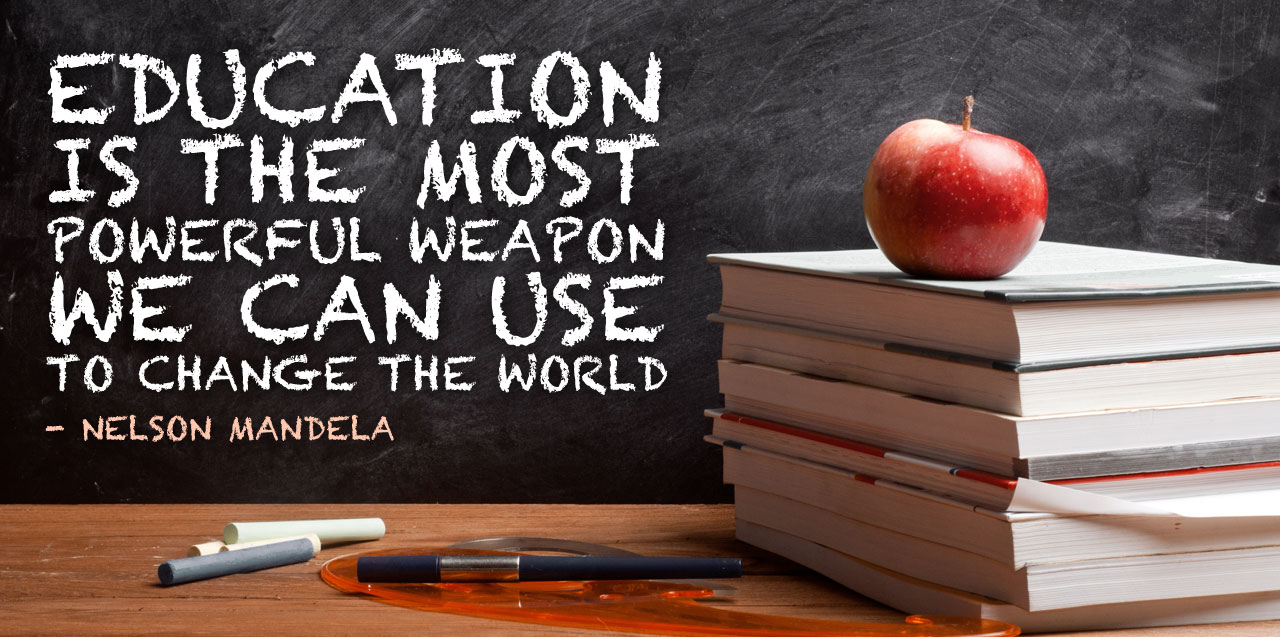
投資家なら「教育」について知っておいて損はありません。
というか、投資家じゃなくても全ての人が知るべきです。
何故なら、最も効率の良い投資が「教育」への投資であり「教育」は世代間で連鎖するからです
Contents
学力の経済学
せっかく「教育」へ投資するなら最もリターンの高い投資をしたいですよね?
その判断の手助けをしてくれるのがこちらの本
こちらは、科学的なエビデンスから「教育」への疑問に解答した本です。
教育経済学者の著者が言うには、日本において教育分野の科学的なアプローチはほとんどされていないとのこと
そのせいで、根拠のない政策が実行され、その後の効果測定もされていないのです。
つまり、税金の垂れ流し(の可能性が高い)
私は、これを読んで「マジか・・もっと考えてくれ・・政治家を教育すべきなんじゃないか」と残念な気持ちになりました。
この本は、今子供がいる人は特に是非読んでもらいたい本です。
「子供は褒めて育てるべきか?」
「ご褒美で釣るようなことをしても良いのか?」
「教育への投資はどの時期が効果が高いのか?」(ネタバレですが、幼少期が最も効果が高く年齢が上がるほど効果がないです)
などのメジャーな疑問に科学的に解答してくれます。
非認知能力の重要性
まず、本のタイトルにもなっている「学力」について少し。
一般的に「学力」というと、いわゆる「テストの点が良いこと」です(これが認知能力)
そして、テストの点が良い人は、頭の良い人というコンセンサス(合意)がこの世の中にはあります。
しかしながら、このコンセンサスが本来の「教育」を歪めている可能性が大いにあります。
つまり、「テストの点数を取る」ことに焦点が当たりすぎて、その他の大事なものが見落とされていないか?ということです。
この本の著者は、認知能力(点数を取る学力)も大事だけど
”非認知能力を伸ばすことが、その人の人生において最も長期的に効果がありリターンの高い教育である”と言っています。
ここで言う「非認知能力」とは、誠実さや社交性、忍耐力などのことで、言い換れば「人間力」とでも呼ぶものになりますね
そりゃそうです。
学校を卒業した後の社会では、テストの点数や偏差値なんてチェックされませんし、その点数が高いからと言って長期的に評価されることもありません。
いくら学校で良い点取れても、実社会で有効に使えなければ意味がないのです。
誤解しないで欲しいのは、認知能力(学力)がいらないということを言いたいのではなく、そのテストで測定された「理解力」や「記憶力」「論理力」を有効活用する土台に非認知能力(人間力)が必須ということです。
先ほど言及した「歪み」とは、
例えば、「勉強のために部活や野外活動を辞めさせる」などの土台の非認知能力を無視して認知能力のみ見て指導をするようなことを指してます。
私も「テストの点数が取れればそれでいい」という教育はおかしいと思います
実際に遭遇したのですが、ろくにコミュニケーションも取れないような「医師」や「教育者」なんて笑えませんよね?
長期的に効果がある非認知能力
著者は、非認知能力の中でも二つの重要な能力を挙げています。
それは
- 自制心
- やり抜く力
です。
「自制心」・・やるべきことを優先する力。
「やり抜く力」・・努力する力
とも言い換えれるでしょうか。人生の成功者はほぼ例外なくこの二つの能力に長けていると思います。
そして、非認知能力の高さは幼少期から老齢期まで長期的に効果があるので、ここを伸ばすことはその人にとって最高の投資となるでしょう。(当然、この二つを持っていれば「学力」も高くなる)
間違った平等主義の弊害
「人間生まれながらに皆平等」
美しい言葉ですね
しかし、この言葉を「能力」という面で解釈すると間違ったことになります。
だって、現実には「能力」は生まれながらに平等ではないので
この前提が大事。
人は生まれながらに「能力」に差があります。
性格だって違う。
これが現実。
なので、皆同じ教育なんてありえませんし、同じ人間になんてなれません。
違うのが当たり前なんです。
昨今「差別だなんだ」とウルサイ時代なので、ことさらに間違った「平等」を押し付けてくる人がいますが本当に害だと思いますね。
(そんな人こそ差別主義者であると個人的には思いますが)
「平等」とは、皆を同じ型に嵌めることではありませんし、別の扱いをすることをタブー視することでもありません。
この本でも例として出てきますが、「皆で手を繋いでゴール」というおぞましい平等主義の象徴のような話に関して面白い事後調査があります。
この教育を受けて育った人間は、「他人を思いやり、親切にし合おうという気持ちに欠ける大人になってしまう」ということが明らかになりました。
よく考えれば当たり前です。
彼らの価値観は皆同じ能力を持って生まれています。
そんな彼らの価値観の中では、事後の差は「努力の差」でしかなく自己責任。
落ちこぼれたら「努力不足のやつが悪いんだよ」で終わりです。
また、いくら努力をしても学校で「手を繋いで一緒にゴール」なんて教育されたら努力をする気がなくなりますよね
「差をつけることが悪いこと」という価値観は人間を歪めます。
能力に差があるのであれば、
例えば、同じレベルの生徒を集めて授業をすることや、特に遅れている子供には特別授業をするなど。
それを前提にした教育が必要になってくる。(この点も日本は研究不足で何が効果的かはまだわからないみたい)
差があることを前提に、できる限りその差を縮める教育が必要になります
結局、家庭環境が大事
まだまだ書きたいことはあるのですが、そろそろまとめます。
教育は、幼少期の教育投資がとても大事です。
そして、人間は皆違うという前提の下
その教育投資は学力のみを上げるのではなく「非認知能力」を伸ばすことを念頭におくべき。
最後に、驚きの「学力」を決めている要素の比率をご紹介します。
遺伝・・・35%
家庭環境・・34%
その他・・・30%(端数は省略)
なんと、遺伝と家庭環境で7割決まるようです。
「その他」に入る学校の要素は30%ほど
更に、ここから分かることは「家庭環境」が34%と学校を含めた「その他」の割合より多いこと
もはや「教育、しつけは学校に任せた」とかいう話は通用しません。
 貧困の連鎖じゃなくて教育環境の連鎖でしょ(投資成績2016/9/17) | assets人生
貧困の連鎖じゃなくて教育環境の連鎖でしょ(投資成績2016/9/17) | assets人生
貧困の連鎖は教育の連鎖
こちらの記事でも言及していますが、学力は悪い家庭環境の連鎖によるところが大きいです。
親の自覚と教育への投資意識が非常に大事。
実際、私は子供の教育をするならまずその親からの教育が効果的だと思ってます。(この意味でより良い教育は全ての人に必要でもある)
親の意識が低いままだと、子供だけ教育したところであまり意味がないでしょう。
国にも効果的な教育政策を期待したいところですが、自分たちの子供がいるなら家での教育にも気をつけたいとこですね








![〔織田信長433年目の真実〕投資でも戦国でも超大事な思考法[資産運用]](http://assetsjin.com/wp-content/uploads/2016/02/88b456d156067b2f322fe31290fee599-150x150.jpg)








