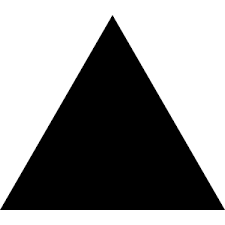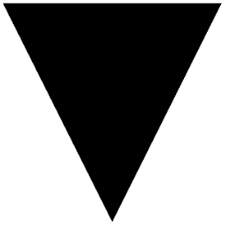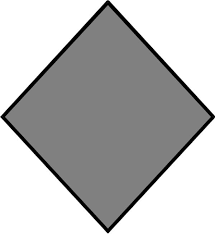こんにちは、imoです。
実は前回の記事がこのブログの600記事目だったみたい。600・・・感慨深いですなー
ただ「おっぱい」と600回書いてくださいと言われてもうんざりするほどの数
メジャーリーグでのホームラン数で言えば、歴代top10にランキングされるほどの本数になります。
600とはそんなある程度偉大な数。
しかしながら、毎週の投資運用報告という無味乾燥な記事でその600記事目を迎えたのはなんかちょっと残念な感じですね。
・・・まあ、個人的な嘆きはこの辺で。
さて、今回はそんな数を書いてきた私の文章の書き方の話を少ししようと思います。
Contents
分かりやすい文章とは?
実はこんな私でも
「論旨が明快で読みやすいです」とか「いつも主張がすっと入ってくる」とか「1万字超えの文章でも長く感じない」とか「上からだけど嫌じゃない(?)」とか言われます。(ドヤァァァア)
これは「何故なのか?」
その理由は、ちゃんと考えて書いているからです。(当たり前)
ただ、「ちゃんと考えて書いている」だけでは意味不明でしょうから、ブログをはじめ、何かを日々書いている人には参考になる文章の書き方について説明していこうと思います。
一応、断っておくと、今回説明する文章は自分で書いて誰かに伝える意図のある文章です。
ブログとかの「まとめ」や単なるノウハウ、手順の説明みたいなモノを書きたい場合は別ですので悪しからず。
ああいうのは、マニュアルの作り方みたいなノウハウでも勉強して外注にでも出せば良いと個人的には思っています。自分で書く必要はない、編集者的な立場でチェックする感じ。
文章の型
シンプルに分かりやすい文章とは、言いたいことが明確な文章です。
その文章全体で何を言わんとしているのか?が分かる。
逆に、文章の中で迷走して最終的に何が言いたいかわからない文章は、読み手にとってストレスになります。
そして、まず根本的に文章を書くからには何か主張が必要。これが大前提。
しかし、多くのネット上の文章を読んでいると、この主張がないパターンが多い・・
「このラーメンうまい!」とか「このゲーム最高」とか
極端に言えばこんな感じの文章です。これらは主張ではない。単なる感想。
よって、文章がボンヤリするのも当たり前。
個人的な日記とか単なる感情の垂れ流しみたいな誰かに読ませることを前提としない文章なら別に良いですが、もしアクセスが欲しいとか、ちゃんと人に読んでもらいたいとか、反応が欲しい、というような場合は当たり前ですが主張が必要になります。
三角型
で、具体的な型の話。
この三角型は、まず主張があってその後色々な話に展開していく形。
英語圏っぽい書き方ですね。
とにかく頭で、「こんなことを言いまっせ」ということを宣言する。その後に例題を出したり、エビエンスを出したり肉付けしていく形。
私の記事の中ではこんな感じ「愚者は経験に学び賢者は歴史に学ぶ」(学びは腑に落ちて初めて意味がある
この形は始めに主張を言うので、その後の肉付けもその主張に沿っているか?を考えながら進めていけます。
たまに見る、始めの主張とは関係ない例題を出してどんどん話が横道にそれて結局何を言いたいのか分からない文章はこの形を意識していないから起きることだと思います。
逆三角型
次は、逆三角形型。
これは、ボンヤリ話に入っていき、最後に主張を持ってくる形。
日本語っぽいですね。枕詞があってその後本題みたいな。
私の記事で言えばこんな感じ
世間話から入って、最後に主張をぶつける形です。
この形の場合も、前段は最後に持ってくる主張に関連している必要があります。関係ない話をダラダラして最後にボンヤリした結論みたいな校長先生の話や結婚式のスピーチみたいなものは全く伝わりません。結論の前に眠くなります
菱形
次は菱形
これは、「主張」→「肉付け」→「主張」みたいな流れの文章です。
実は、私が一番使うのはこの型。上の二つのパターンはあまり使いません。あと、今回みたいに冒頭でどうでも良い短い話から入って、それがなんとなくテーマに繋がるみたいな導入も結構使います。(導入後は菱形。今回はノウハウ的なまとめ記事なのでちょっと変形)
この型の私の記事はこんな感じ
例に出したいくつかのブログ記事は適当に目に付いたやつを貼っただけなので、もっと型が分かりやすい記事も探せばあると思います。興味があれば他の記事も読んでみてどういう構成になっているか?を考えてみてください。
型はこんな感じ。ぶっちゃけ、三角や逆三角は無視して最後の菱形を意識して書くのが良いかなと思います。
で、繰り返しになりますが、主張がないと形自体が出来ないので注意していください。
イタイ、うざい、嫌われる文章
多くの人にイタイ、うざいと思われる文章もたまに見ます。
あえて、そういう文章にしているなら良いですが、特に考えずにそんな文章を書いているなら考え直したほうが良い。面倒なやつにからまれることに繋がります。そして、自分が読んでほしい人に届かなくなります。
色々この原因はあるんですが、一番大きいのは「文章の中身と表現のギャップが大きい場合」でしょう。
大した話でないのに表現だけ大げさだったり、一発で過剰とわかるような賞賛とか成功トークとかとか
例えばこんなやつw
「もしも村上春樹が意識の高いデブで、食レポを書いたら(焼肉編)」
「なら――」と彼女は言った。「あなたはハラミが好きなの?」
「とても難しい質問だ」と僕は言った。「でも好きな小説なら言える」
「小説?」
「そう、小説。僕は雨の日の昼下がりに、出鱈目にページを開いて読み始めるスコット・フィッツジェラルドの『グレート・ギャツビー』が好きなんだ。」
彼女はちょっとだけ首をかしげた。そして舌の上でミノを転がした。僕は少し驚いて彼女の顔を見た。
「なかなかうまくいかないものね」「なかなかうまくいかない」と僕は言った。
これは完全にウケ狙いなのでただただ面白いですが、こんな感じの書き方や喋り方を真面目にやっているならイタイですよね?
極端な例を出したので、よくありがちな例も一つ。
特に男性はやりがちなんですが、「〜であろう」とか「〜だと考えられる」というような重々しい語尾を使う場合。
ただ、これらの語尾を使うのがヤバいということではなく、そんな語尾に耐えうる内容の文章であるのか?という所が問題。
ツイッターとかFacebookなどのSNSでも、大げさな表現を使う人は多いです
ただ飲んだだけなのに「最高の仲間と人生に一度しかないこの時間に乾杯!」とか
ただ名刺交換しただけなのに「素晴らしい人と会いました。今後のビジネス展開を考えるとワクワクします。世界を変えるビジョンが見えてきました!」とか
文章で読み手をフィルタリングする
一方であえて読んで欲しい人に合わせて表現を調整することもあります。
文章の内容も合わせてこれはやるんですが、簡単に言えば読んで欲しい層が一番共感しそうな書き方をする感じ。
「あえてイタイ感じの書き方をしているなら良い」と言ったのもこの意味です。そういう大げさな表現やウェイウェイした雰囲気の層に届けたいのならそういう表現をするべきなのです。
ちなみに、私はこのブログでもメルマガでも一貫して同じ読者層に届くように書いていて、その成果なのか変な人はほぼきません。メルマガではより実感することですが、本当に質の良い人が集まってきていると思っています。
コメントも今は承認制にしていますが、実は変なコメントはほぼゼロであまり意味をなしていません。(過去に一人頭おかしい人が頻繁に書き込んできたのでその対策でした)
「ネットで書くからには色々な人が読んでいる、批判は必ずある。」
これは確かにそうなんですが、文章の書き方によってある程度その批判も小さく出来るのです。
以前、ツイッターで書いた気がしますが、情弱を相手に金儲けしている人はあえて情弱層が反応する表現、言葉を使用しています。
例えば、「何もしなくても確実に大儲け!」「不労所得!」「簡単、短時間で100万円!」「バカでもできる」「努力は必要ありません」「魔法の」「秘密の」「裏情報」などなど
こんな言葉に反応する人たち
この層は騙しやすいですが、被害者意識が強く大きなリスクも抱えます。倫理観とかなくして刈り取る意識の人には良いお客さんですが、まともな感覚の人には面倒なお客さんですね。
こんな感じで、実は文章を書く方が読み手をフィルタリングすることが出来ることも覚えておいて下さい。
自分が伝えたい人はどのような言葉や表現を普段使っているのか?をよく観察するのです。
SNSではこれは顕著に分かりますよ。
ユーモアの出し方
文章にはユーモアが必要です。
ガチガチの論文みたいな文章は勉強になるかもしれませんが楽しくはないですよね?
真面目すぎる文章は脳が疲れます。
適度に食休みを入れないと逆に食が進みません。
しかし、さっきのイタイ表現のように違和感のあるふざけた表現や言葉を入れるのもNG
では、どうするか?
ポイントは全体の雰囲気とディティールです。
普段の言葉使いの中でちょっと変わった表現を入れたり、視点を変えた言葉を使う・・などちょっとした自分なりの変化をつけてみる。
それだけで十分ユーモアを感じられます。ちょこちょこそういう小さな変化やヌケを入れて全体として面白かったと感じてもらう。
これが上手く機能すれば長い文章もスッと読める感じを与えられます。
または、もうキャラが出来ていて読者層もそこに合わせているのならネタっぽい全体のふざけた雰囲気の中で少しまともなことを言うみたいな逆パターンもありますね。
変なノリや無理やりなユーモアはいらないのです。あくまで全体の雰囲気とディティールの変化で匂わすくらいで十分。
他にも色々ありますが、取り敢えずこんなとこで。
以上、自分の伝えたい人へ向けて文章を書く時に注意する点でした。